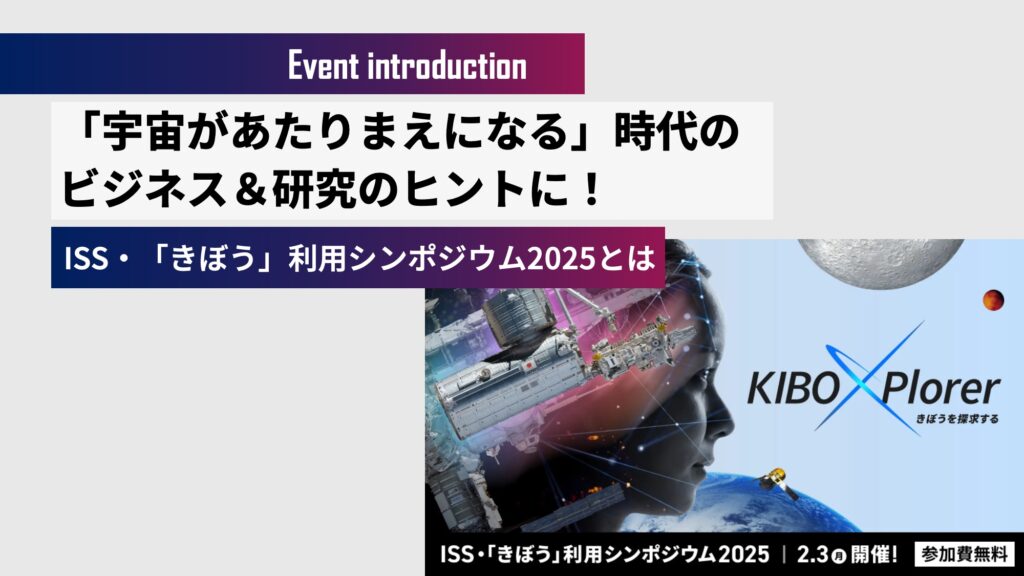
2025年2月3日(月)、東京都港区の東京ポートシティ竹芝とオンラインにて、国際宇宙ステーション(ISS)・「きぼう」利用シンポジウム2025が開催されます。
このシンポジウムは、2018年から宇宙航空研究開発機構(JAXA)が主催しているもので、今年で8回目の開催。宇宙ビジネスへの注目が集まる今、最新情報を入手するのに適したイベントであるといえます。
ISS・「きぼう」を利用するとはどういうことか? ビジネスにどうつながるのか?
この記事では、特に宇宙ビジネスに関心をもつ方に向けて、シンポジウムの見どころをご紹介します。
目次
地上400kmの宇宙実験施設、国際宇宙ステーション
「国際宇宙ステーション」(ISS)とは、地上約400キロメートル上空の地球低軌道(LEO)を周回する有人実験施設です。アメリカ、ロシア、日本、カナダ、欧州の国際協力により運営されており、常時5〜7名の宇宙飛行士が滞在しています(2025年1月時点ではNASA宇宙飛行士4名、Roscosmos宇宙飛行士3名の計7名が滞在しています)。
このあと説明する日本実験棟「きぼう」のほか、複数のモジュールによって構成されるISSはサッカーコート1面分ほどの広さがあり、微小重力というLEOの特異な環境を活かしてさまざまな実験・研究が行われています。
しかし、1998年に建造が開始され、2011年7月に完成したISSは2030年に退役することが決まっています。主な理由は老朽化によるもので、役割を終えたISSは地球の大気圏に再突入させると計画されています。
現在は、このISS退役後の世界、「ポストISS」を見据え、民間企業が主体となった宇宙ステーション開発構想がアメリカを中心に進んでおり、日本を含めた各国が、人工衛星を用いた通信や地球観測、さらには軌道上でのサービス、探査など、LEO領域のビジネス活用に取り組もうとしています。
世界中で宇宙ビジネスや宇宙環境を利用した研究開発に注目が集まっている背景には、こうした事情もあるのです。
企業の研究開発の場でもある、 ISSの日本実験棟「きぼう」
ゆくゆくはISSがなくなるとはいえ、退役までにはあと5年ほどあります。
それまでの間にISSを使い尽くし、近い将来いっそう本格化するであろう宇宙ビジネスの時代に備えることは重要であり、そのISSに日本の施設があるということは、世界的に見ても大きな強みであるといえます。
全長約11.2メートル、直径4.4メートルの円筒形をした日本実験棟「きぼう」は、実験スペースとしてはISS内で最大級の広さをもった施設で、「きぼう」ではこれまでに、さまざまな研究機関や企業が実験・研究を行ってきました。
例として、創薬ベンチャーのペプチドリームは、特殊なタンパク質の結晶化実験を実施。地上ではつくれない高品質な結晶の生成に成功し、新薬開発に向けた重要なデータを得ました。また、宇宙食の開発実験も行われており、日清食品やハウス食品といった身近なメーカーも宇宙利用に参画しています。
このほかにも「きぼう」には、健康長寿研究のためのマウス飼育設備や、細胞医療のための研究装置、材料研究を行うための静電浮遊炉、超小型衛星放出装置など、さまざまな機能・設備を備えています。
宇宙での研究・ビジネスの最前線に立つスピーカーが集結 〜宇宙ビジネスと関連の深い見どころは?
ISS・「きぼう」利用シンポジウムでは、宇宙環境を利用した研究・ビジネスに第一線で取り組む官民のスピーカーが国内外から登壇。各セッションの議論を追うことで、宇宙利用の現状から今後の見通しまで、最新動向を幅広くキャッチすることができます。
ビジネス実現に向けた技術開発動向がわかる、「ポストISSへ向けた新たな取組み – 宇宙戦略基金とコミュニティ形成」
特に宇宙ビジネス関連の情報を得たい方は、15:05からの第4部「ポストISSへ向けた新たな取組み – 宇宙戦略基金とコミュニティ形成」がおすすめです。
今年度から開始された「宇宙戦略基金」(参考記事)は、「輸送」「衛星等」「探査等」の3分野にわたり、スタートアップをはじめとする民間企業や大学等研究機関が最大10年間、大胆な技術開発に取り組むことを支援する枠組みです。
すでに採択事例も出始めており、今回のシンポジウムでは基金の現状とともに、採択企業のプレゼンテーション・ディスカッションを聞くこともできます。今後宇宙ビジネスに取り組みたいと考える方にとっては必聴のプログラムです。
健康・医療関連の最新動向がわかる、「加速するきぼうライフサイエンス研究」
また、新型コロナウイルス感染症の流行や高齢化などで需要の高まるライフサイエンス(生命科学)領域での研究やビジネスに取り組む方にとっては、13:15からの第3部「加速するきぼうライフサイエンス研究」も見逃せません。
実際に「きぼう」で宇宙実験を行った研究者によるプレゼンテーション・ディスカッションが行われるこのプログラムでは、なかなか触れることのできない宇宙環境での実験・研究のリアルを知ることができるでしょう。
なお、シンポジウムのプログラムは2024年3月に改定された「きぼう利用戦略 第4版」に沿っていますので、これに目を通したうえで参加すれば理解度をより上げることができるでしょう。

Credit: JAXA
また、より気軽にシンポジウムを聴講したい方は、シンポジウムの公式アンバサダーを務めるロケット工学アイドルVTuber・宇推くりあさんによる副音声配信を視聴することもおすすめです。
ISS・きぼう利用シンポジウム2025 開催概要・プログラム
プログラム
[総合司会]
弘竜太郎(日本テレビ放送網株式会社 コンテンツ戦略本部コンテンツ戦略局 アナウンス部)
10:30〜 第1部 オープニング
登壇者
松浦真弓(国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構〔JAXA〕理事)
調整中(文部科学省)
Robyn Gatens(アメリカ航空宇宙局〔NASA〕国際宇宙ステーション部長/商業宇宙飛行部長代行)※ビデオメッセージ
白川正輝(国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構〔JAXA〕有人宇宙技術部門 宇宙環境利用推進センター長)
古川聡(国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構〔JAXA〕有人宇宙技術部門 宇宙飛行士グループ 技術領域上席 宇宙飛行士)※ビデオメッセージ
11:50〜 第2部 HTV-X -日本の技術でつなぐ宇宙への架け橋
登壇者
伊藤徳政(国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構〔JAXA〕有人宇宙技術部門新型宇宙ステーション補給機プロジェクトチームプロジェクトマネージャ)
弘竜太郎(日本テレビ放送網株式会社 コンテンツ戦略本部コンテンツ戦略局アナウンス部)
13:15〜 第3部 加速するきぼうライフサイエンス研究
登壇者
<前半>
Ryan L. Prouty(アメリカ航空宇宙局〔NASA〕)
白川正輝(国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構〔JAXA〕有人宇宙技術部門宇宙環境利用推進センター長)
<後半>
山本雅之(東北大学 教授/東北メディカル・メガバンク機構 機構長)
村谷匡史(筑波大学 医学医療系教授)
有竹浩介(第一薬科大学 薬学部 薬品作用学分野 教授)
[モデレーター]黒田有彩(宇宙タレント)
15:05〜 第4部 ポストISSへ向けた新たな取組み – 宇宙戦略基金とコミュニティ形成
登壇者
<前半>
中須賀真一(文部科学省 国際宇宙ステーション・国際宇宙探査小委員会 主査)
小川志保(国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構〔JAXA〕有人宇宙技術部門 事業推進部 部長)
<後半>
高田正治(株式会社IHIエアロスペース 経営企画部 事業開発グループ 課長)
山本雄大(株式会社日本低軌道社中 代表取締役社長)
井上実沙規(株式会社日本低軌道社中 利用開発部長)
山崎秀司(Space BD株式会社 ISS船内プラットフォーム事業ユニット 事業ユニット長)
村上一馬(三菱商事株式会社 宇宙航空機部 課長)
佐藤巨光(SORAxIO/有人宇宙システム株式会社 ISS利用運用部 部長) ほか
[モデレーター]米津雅史(一般社団法人クロスユー 事務局長)
17:10〜 第5部 クロージング
登壇者
白川正輝(国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構〔JAXA〕有人宇宙技術部門 宇宙環境利用推進センター長)
小川志保(国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構〔JAXA〕有人宇宙技術部門 事業推進部 部長)
宇推くりあ(ロケット工学アイドル VTuber)
開催概要
日時:2025年2月3日(月)10:30~18:00(予定)
会場:東京ポートシティ竹芝 1階 ポートホール(105-0022 東京都港区海岸1丁目7番1号)
およびYouTube配信
特設サイト:https://iss-kibo.space/2025/
参加費:無料(会場観覧のみ事前登録制)
事前登録:https://iss-kibo-space2025.peatix.com
主催:国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構(JAXA)
事務局:株式会社デジタルブラストコンサルティング






