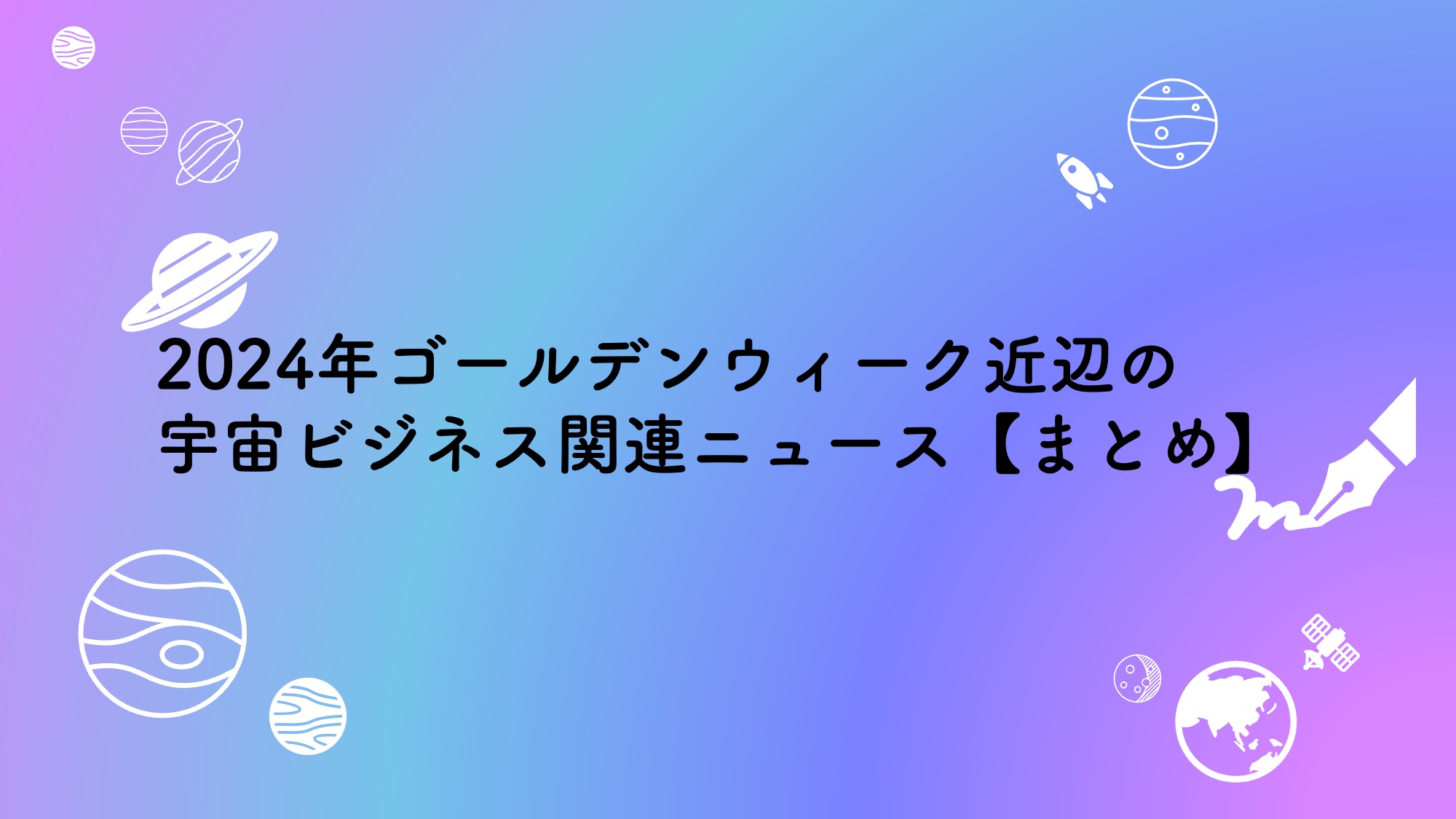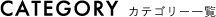日本における宇宙ビジネス発展の起爆剤として期待されている「宇宙戦略基金」。
10年間で1兆円を投じて今後の日本の宇宙開発・宇宙ビジネスの基盤となる技術やビジネスモデルを構築するこの事業にかかわることができるのは、長く宇宙産業に携わってきた企業だけだと思われがちですが、そうではありません。
今回は、非宇宙企業でありながら宇宙戦略基金第一期事業の代表機関として採択された株式会社INDUSTRIAL-Xのお二人に、採択の背景と、事業を通じて目指す「宇宙のものづくり」の姿を聞きました。

株式会社INDUSTRIAL-X 代表取締役CEO
1997年松下電工(現 パナソニック)入社、宅内組み込み型の情報配線事業の商品企画開発に従事。その後、介護系新規ビジネス(現 パナソニックエイジフリー)に社内移籍、製造業の上流から下流までを経験。さらに、複数のコンサルティングファームを経て、2014年にシスコシステムズに移籍、ビジネスコンサルティング部門のシニアパートナーとして同部門の立ち上げに貢献。一貫して通信/メディア/ハイテク業界中心のビジネスコンサルタントとして新規事業戦略立案、バリューチェーン再編等を多数経験。
2016年4月よりウフルIoTイノベーションセンター所長としてさまざまなエコシステム形成に貢献。2019年4月にINDUSTRIAL-Xを創業、代表取締役を務める。2020年10月に広島大学AI・データイノベーション教育研究センター客員教授就任。著書に『図解 クラウド早わかり』(中経出版、2010)、『DX CX SX』(クロスメディア・パブリッシング、2022)など。

株式会社INDUSTRIAL-X 事業開発リーダー
新卒で西条市役所(愛媛県)に入庁し、公務員として約10年間勤務。その間に国土交通省外局の観光庁へ2年間出向し、インバウンドの地方誘客を担当して北海道釧路市をはじめとするモデル都市創出の支援に従事。市役所への帰任後は観光部門に1年間配属されたのち、農業部門へ異動。スタートアップ企業とともに農業領域における衛星データ利活用の実証実験などに取り組む。その後、INDUSTRIAL-Xに入社し、現在は宇宙戦略基金プロジェクトの担当者として、非宇宙産業と宇宙産業の橋渡し役を務める。
目次
大きく転換する産業構造、新たな「ものづくりの場」としての宇宙
製造業のDXを掲げ、八子氏が2019年に創業したINDUSTRIAL-X。
製造業における企業変革のコンサルティングやDX/AI導入支援を手がける同社は、今年2月、宇宙戦略基金第一期・経済産業省計上分の技術開発テーマ「衛星サプライチェーン構築のための衛星部品・コンポーネントの開発・実証」のうち、「衛星サプライチェーンの構築・革新のための横断的な仕組みの整備に向けたFS(フィージビリティ・スタディ:実現可能性調査)」の委託先として採択されました。
同テーマの研究代表者でINDUSTRIAL-X 代表の八子氏は、早い段階から「宇宙」を新たな事業領域として意識していたと明かします。
「起業2年目の2020年、当社は『スペース・ツイン®構想』を発表しています。地球上のアナログ空間をデジタル空間に再現するデジタルツインがあるなら、宇宙空間でも同じことができるのではと考えたのです。現に、当時からSpaceXやBlue Originといった宇宙開発企業はシミュレーションベースでロケットを開発し、打ち上げていました。デジタル空間でシミュレーションしたものを宇宙へもっていくことができるのであれば、デジタルツインの次はスペース・ツインだと考えたわけです」(八子氏)
そして、この構想の背景には、自社のDXコンサルティングというビジネスは中長期的に見ればこれを達成する企業が増えることで縮小していくこと、そして日本の製造業は、業界構造の転換によりマーケット縮小に直面するという危機感があったと語ります。
「電気自動車の時代が進展するにつれ、ガソリン車で約3万点ある部品点数のうちの1万点がなくなることになり、自動車産業を支える金属加工業の方々が仕事を失う恐れがあります。こうしたことが予測される中では、新しいビジネスをつくることが国として非常に大きなミッションだと思っていました。金属加工業の技術や知見を活かせるマーケットはないか考えたとき、それは宇宙しかないだろうと思ったのです」(八子氏)
ガンダム世代でもあるという八子氏。「ガンダムの世界では宇宙でモビルスーツが飛んでいたし、スペースコロニーが回っていたじゃないですか」と笑います。

宇宙ビジネス参入をねらう中、「宇宙戦略基金」挑戦のチャンスが
構造転換にさらされる製造業・金属加工業に新たな道を示すべく掲げられた「スペース・ツイン®︎構想」ですが、当時はまだ創業2年目。宇宙ビジネス参入のタイミングをうかがっていた八子氏のもとにいくつかのピースが集まり、転機が訪れたのは2024年でした。
一つ目は、「スペース・ツイン®構想」を掲げた2020年に、宇宙スタートアップ・Synspectiveの創業者であり、システムエンジニアリングの専門家である慶應義塾大学教授の白坂成功氏が同社のアドバイザー(後に社外取締役に就任)として参画したことです。もともと二人は経済産業省の委員として面識があり、白坂氏もかねてから宇宙産業拡大のためには製造業の参入が必要、と考えていたために意気投合。八子氏は宇宙産業や宇宙ビジネスに関するアドバイスを受けるようになったのです。
そんな中、宇宙戦略基金の取り組みが始動。技術開発テーマとして、製造業と大いにかかわる「衛星サプライチェーンの構築・革新のための横断的な仕組みの整備に向けたFS」の公募が開始されました。
しかし、経営者に宇宙ビジネスへの思いがあり、また宇宙領域のアドバイザーがいるからといって、大きな額が投じられ、かつ国として初めて行われる事業への応募に踏み切ることは容易ではありません。INDUSTRIAL-Xとして宇宙戦略基金に挑戦することになった背景には、まだ重要なピースがありました。
それは、社内に自治体・行政勤務経験者が在籍していたこと。現在、同社サイドで基金プロジェクトを担当する安藤氏は、地方公務員として10年あまり勤務。さらに中央省庁への出向経験ももっています。自治体として国の公募に応募する側、省庁としてさまざまな応募を受け付ける側、双方の経験をもっていた安藤氏がいたことは、宇宙戦略基金の応募に際して大きな強みになったといいます。
そして、興味深いのは、衛星サプライチェーンという深い業界知識や経験などが求められるであろう領域にもかかわらず、この技術開発テーマでは、非宇宙企業であるINDUSTRIAL-Xが代表機関となっている点です。同社はこのフィージビリティスタディを、長年の衛星開発経験をもつNEC、三菱電機とともに進めていく座組を提案しています。
この座組について、八子氏は、当初は自社がこれら企業の下につくかたちでの参画を想定していた、と率直に語ります。しかし、応募に向け各者で体制を検討する中で、衛星開発にかかわるメーカー間を取り持って標準化・効率化を検討するためには、衛星開発を手がけておらず、ある意味中立な立場にあるINDUSTRIAL-Xが研究代表者となることが適切なのではないか、という判断に落ち着いたのだといいます。
非宇宙企業ながら、同社が第一期の宇宙戦略基金を受託できたのは、経営者である八子氏が宇宙ビジネス参入を意識している「Ready」の状態であったことと、宇宙業界の専門家である白坂氏とのコネクションがあったこと、社内で入札等に対応できる経験・スキルのある人材がいたこと、そして、INDUSTRIAL-Xが製造業のDXコンサルタントとして「ものづくり」の観点から衛星製造をアップデートするための知見を備える企業だったということが理由にあるといえるでしょう。

衛星の「量産」に向け、なにをどう標準化していくべきか?
今回同社が採択されたフィージビリティスタディは、衛星の開発工期を約3分の1に短縮することに資するアーキテクチャの共有、そして開発プロセスの標準化を検証することが目的です。工期が3分の1になれば、これまでの開発期間で3倍、衛星を製造できるようになるといえ、現在急速に需要が増加している衛星コンステレーションの構築、ひいては宇宙ビジネスの市場拡大にもつながります。
実際、国内外でさまざまな企業が衛星の量産を掲げて新工場の設立や生産設備の増強を進めています(参考記事1、参考記事2)。
フィージビリティスタディはまだ始まったばかりですが、元来、人工衛星は一点ものの要素が強く、各社が個別に、オーダーに応じて開発を進めてきた経緯があります。どこを「標準化」するのか、そしてそれをどのように進めていくか、八子氏はこう説明します。
「宇宙産業が拡大する中、標準化やモジュール化の必要性は各社が感じています。やらなくてはいけないことだという認識は共通していますが、宇宙産業は防衛領域とも関連が深いため、開示できない情報もあり、標準化できる部分とそうでない部分があるのが難しいところです。つねづね白坂先生からお聞きしますが、『競争領域』と『協調領域』をどう分けるかが、標準化・モジュール化、もしくは物事をシステムとして捉えるときの最大のポイントです。切り分けた中で標準化の対象になるところはどこか、議論を進めていくと、次第に『バス部は御社が強いよね』『通信はそちらが得意でしょう』『そういえば、前のプロジェクトでそういう組み方をしていましたよね』という話が出てきます。少しずつ糸口が見えてきている状態で、いけそうだという手応えを感じています」(八子氏)

明るい兆しがある一方、標準化を考える際は欧州など海外の規格なども参照する必要があります。これからの課題として安藤氏は次のように指摘します。
「国内で規格をつくっても、どれだけ使ってもらえるかは皆が課題に感じているところです。また、現状、海外からしか調達できない部品もあるため、日本独自の規格をつくったとしても、結局そことの調整が必要になるという問題はあります。海外からの調達といった点も含め、どうすり合わせていくべきか、今まさに議論が必要な部分だと感じています」(安藤氏)
フィージビリティスタディに取り組んで改めて、宇宙のものづくりはいまだ量産というフェーズに至っていないことを認識したという八子氏。
量産を実現するためには、素早く失敗を繰り返し学ぶのを許容する姿勢も必要だと語ります。
後編に続く
【編集部よりお知らせ】ニュースのまとめや新着記事をお知らせ!メールマガジン(不定期配信)のご登録はこちらから